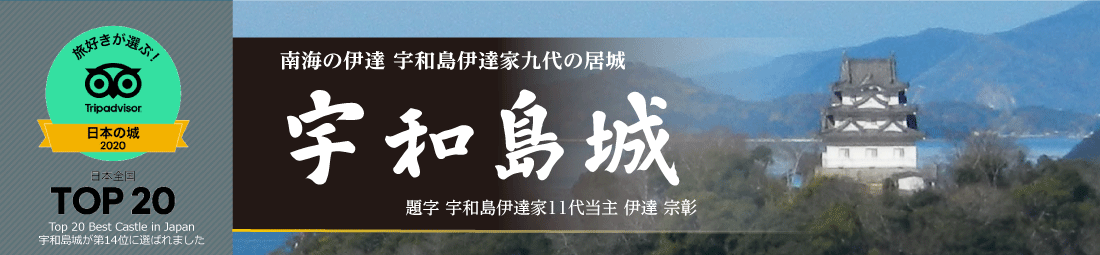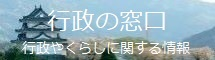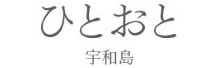本文
宇和島城のあらまし
現存12天守の一つがそびえ立つ宇和島城は、慶長(けいちょう)20(1615)年に伊達政宗(まさむね)の長男、秀宗(ひでむね)が入城後、明治を迎えるまで"西国の伊達"9代の居城でした。
国が定める「重要文化財(建造物)」に指定されている天守は、宇和島伊達(だて)家2代藩主の宗利(むねとし)が寛文(かんぶん)6(1666)年頃に建築したもの(寛文天守)です。かつて同所には、築城の名手として有名な藤堂高虎(とうどうたかとら)が慶長6(1601)年に建築した天守があり、幕府には修理の名目で届出をしましたが、天守台の石垣を含めて宗利により全面的に建て直されたため、その姿(慶長天守)は絵図でしか窺(うかが)い知ることができません。
|
寛文天守(現存) |
慶長天守 |
|---|---|
|
伊達 宗利 建築 |
藤堂 高虎 建築 |
|
寛文6(1666)年頃 完成 |
慶長6(1601)年 完成 |
|
・3重3階 ・層塔型 ・白漆喰総塗籠 |
・3重3階 ・望楼型 ・下見板張 |
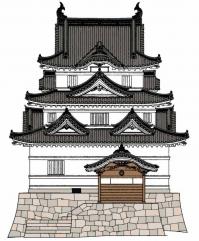 |
|
【現存12天守】
江戸時代には170ほどの天守がありましたが、現在では12棟しかない貴重な建造物で、すべて国指定の文化財となっています。
| 国宝 | ・松本城(長野県)・犬山城(愛知県)・彦根城(滋賀県) ・姫路城(兵庫県)・松江城(島根県) |
|---|---|
| 重要文化財 | ・弘前城(青森県)・丸岡城(福井県)・備中松山城(岡山県) ・丸亀城(香川県)・松山城(愛媛県)・宇和島城(愛媛県)・高知城(高知県) |
 宗利は天守のほかに、櫓(やぐら)や門なども改修しましたが、堀や石垣などの縄張(なわばり)は高虎のものをほぼ引き継いでいます。堀については、幕府隠密(ばくふおんみつ)が五角形を四角形と見誤って報告した史実から、高虎の巧みな縄張として語られることとなる“空角(あきかく)の経始(なわ)”の話が生まれました。明治以降、堀はすべて埋められましたが、その名残は今の道路に見ることができます。石垣については、高虎から伊達家によるものまで新旧さまざまな石垣が残されています。詳しくはこちらへ。これらの縄張がほぼ当時の姿をとどめており、城全体も国の史跡として指定されています。
宗利は天守のほかに、櫓(やぐら)や門なども改修しましたが、堀や石垣などの縄張(なわばり)は高虎のものをほぼ引き継いでいます。堀については、幕府隠密(ばくふおんみつ)が五角形を四角形と見誤って報告した史実から、高虎の巧みな縄張として語られることとなる“空角(あきかく)の経始(なわ)”の話が生まれました。明治以降、堀はすべて埋められましたが、その名残は今の道路に見ることができます。石垣については、高虎から伊達家によるものまで新旧さまざまな石垣が残されています。詳しくはこちらへ。これらの縄張がほぼ当時の姿をとどめており、城全体も国の史跡として指定されています。
※左の絵図:元禄16(1703)年の城下絵図(公益財団法人宇和島伊達文化保存会所蔵)
【城全体の特性】
宇和島城は立地(りっち)や構造(こうぞう)から2つの特性をあわせもっています。
・水城
海岸、川、湖や沼の近くに築いて、その水を防御(ぼうぎょ)に利用する城
・平山城
天守や郭(くるわ)などがある丘と御殿(ごてん)や屋敷(やしき)などのある麓(ふもと)の平地が
一体化して機能する城
【歴代城主】
・宇和島伊達家9代 :慶長20(1615)年~慶応4(1868)年
初代 秀宗(ひでむね) 2代 宗利(むねとし) 3代 宗贇(むねよし)
4代 村年(むらとし) 5代 村候(むらとき) 6代 村寿(むらなが)
7代 宗紀(むねただ) 8代 宗城(むねなり) 9代 宗徳(むねえ)
・富田信高(とみたのぶたか): 慶長13(1608)年~慶長18(1613)年
・藤堂高虎: 慶長元(1596)年~慶長13(1608)年
| 種 別 | 指定名称 | 指 定 日 |
|---|---|---|
| 重要文化財 | 宇和島城天守 | 昭和9年1月30日 |
| 史跡 | 宇和島城 | 昭和12年12月24日、平成28年3月1日追加指定 |