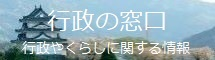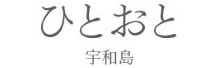本文
市指定 ヤブツバキ
市指定天然記念物
 ヤブツバキ 一本
ヤブツバキ 一本
- 所在地 津島町上畑地小祝
- 所有者 個人
- 指定日 平成一三年六月二二日
このヤブツバキ(藪椿)は津島町上畑地、小祝の谷川沿いにある。主幹は直立し、途中(地上八五cm)から三本に枝分かれしている。根回り三・○m、幹回り二・四m、枝張り一二・二m、高さ一二mである。樹勢はすこぶる良好で小枝の発育も旺盛、春には多数の紅色花が咲きほこる。
この付近には「四国の道」が通り、四国八十八箇所巡礼の遍路姿の情景も途絶えることがない。
このヤブツバキについては、つぎのような伝承がある。
「昔のことである。年の瀬も近いある雪の日の夕方、遍路道で一人の坊さんが倒れていた。昔のことゆえホゴでかいて自分の家に連れて帰り、手厚く介護した。しかし、一向によくなる気配はなく、正月を迎えることになった。元旦の朝、雑煮を枕元に持っていったが、それも食べず、ついに息を引き取った。遺体にはふとんをかけて、家の裏に穴を堀り埋葬した。一日が経ち二日目のこと、遺体にかけていた布を取ると、なんとその遺体が、驚くことに金銀に変わっていた。その場所にこの金銀を埋めると、やがて、そこにはヤブツバキが二、三年でがっしりと根を張り、現在の大椿に生長した」という。
小祝のヤブツバキの生育地付近の環境は山間部の谷川沿いで、一帯はシイ・アラカシを主体とする常緑広葉樹林からなる。
このヤブツバキの周辺にはサクラやモミジなどの庭木が育ち、桜花・紅葉が楽しめる。樹下にはセンリョウ・マンリョウ・ナンテン・シャガなどが生え、風情をそえる。また近隣の谷川では緑濃きセキショウの葉が清冽な水に洗われ、豊かな自然環境が保持されている。
〔ヤブツバキについて〕ヤブツバキはツバキ科に属す。日本に自生するツバキの仲間には、ヤブツバキのほかにユキツバキやヤクシマツバキがある。サザンカやチャノキはツバキ属である。
ヤブツバキは本州・四国・九州・沖縄・東アジアに分布する。四国では海岸部から深山にわたり生育範囲がきわめて広い。用途は、庭木・鉢物・建築・器具・彫刻・椿油などさまざまである。
ツバキ(椿)の名は古事記、日本書紀、万葉集にも出ており、古代では神秘の木とされていた。
ツバキが美の対象になったのは鎌倉時代以降である。江戸時代にはツバキの愛好熱が高まり、研究書や「品種目録」が盛んに出版された。現在も数々の品種が出回り、愛好者が多い。