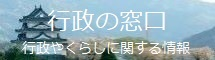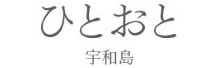- 生活・くらし
- 防災・安全
- 健康・医療・福祉
- 子育て
- 教育・社会活動
- 事業者の方へ
- 市政情報
本文
市指定 桜田千本の歌碑
市指定記念物(史跡)
 桜田千本の歌碑
桜田千本の歌碑
- 所在地 三浦東無月
- 所有者 個人
- 指定日 昭和四九年二月一二日
三浦東の無月から山越えで石引・来村に通じていた旧道の登り口から、少し登った所に、高さ約一m、幅〇・一五mほどの歌碑が建っている。道路に向かった面には、
「山あひの海は扇のすかたにてなみに絵かける富士の面影」と刻まれている。海に面した方には、「明和丙戌夏日千本建」と記され、峠に向かった面には、「簡要石」と書いてある。
歌は、この谷から眺めた三浦湾を扇の姿に見立て、その波に映る三浦権現山を富士山になぞらえて詠んだものであろう。簡要とは、扇の要という意味であり、明和丙戌は、明和三(一七六六)年にあたる。
千本は、桜田玄蕃親翰の雅号で、金剛山大隆寺の西の谷にある大桜田家の墓地の五輪塔に、
「俗名桜田玄蕃親翰 別号千本 称飛香舎 千本院殿飛香道塵居士 明和五戊子十一月二十八日於江戸府卒 行年四十五」と刻まれている。
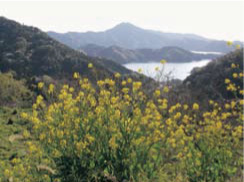 親翰は、宇和島藩中興の英主といわれた五代藩主伊達村候に仕えて、重用せられた家老で、その死にあたっては、村候自ら墓に詣でたと、『鶴鳴余韻』に記されている。また、村候の江戸出府のとき幕府の要職にある高官を招待した際、老中から伊達藩家中の代表として、一番最初に盃を賜わっていることも『御年譜微考』にある。
親翰は、宇和島藩中興の英主といわれた五代藩主伊達村候に仕えて、重用せられた家老で、その死にあたっては、村候自ら墓に詣でたと、『鶴鳴余韻』に記されている。また、村候の江戸出府のとき幕府の要職にある高官を招待した際、老中から伊達藩家中の代表として、一番最初に盃を賜わっていることも『御年譜微考』にある。
親翰は、この歌碑を建てて二年後に江戸で亡くなったのであるが、これは、市内最古の文学碑であるとともに、県内でも古い価値ある歌碑でもある。