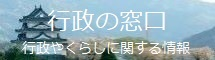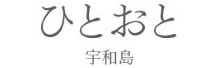本文
教育長通信「あおぞら」vol.9 遊びは学び
「非認知能力」という言葉を耳にされたことはありますか。これは、学力テストなどで測れる「認知能力」とは異なり、例えば自己肯定感やコミュニケーション能力、忍耐力、好奇心、協調性など、人間としての生きる力を表すものです。近年、国内外でこの「非認知能力」の重要性が注目され、特に幼児期の教育がその基礎を形成する重要な時期であると言われています。
幼児期は人間の成長の中でも特別な時期です。この時期に子どもたちは、遊びや日々の生活を通して、自分自身を見つけ、他者と関わりながら社会性を育んでいきます。砂場で一緒に遊ぶ中での役割分担や、おもちゃの貸し借りを通じた交渉、失敗した時の悔しさや工夫による成功体験など、これらの経験が非認知能力を育む土台となります。こうした能力は、長い人生の中で、試練に立ち向かう力や新しい環境に適応する力を支えてくれるものです。
私は、一年前まで公立幼稚園に勤務していました。それまで長年携わってきた小学校教育から幼児教育へ。まさに、「目から鱗」の出来事が毎日たくさんありました。幼児期の子どもたちは、様々な体験を通して「学びの芽」を育んでいきます。そしてそれは、保育者の関わりや環境構成によって大きく左右されます。そこには、子どもたちのつぶやきや行動、ちょっとした変化を見逃さず対応する保育者の力量が求められます。


幼児期の子どもは素晴らしい感性を持っています。こんなことがありました。雪が運動場に積もった朝のことです。子どもたちは、大喜びで雪合戦や雪だるまづくりをして楽しんでいました。けれども、一人だけその遊びに参加せず、植木鉢の近くでじっと座り込んでいるA児がいました。「どうしてみんなと一緒に遊ばないんだろう。」そう思って遠くから何回か声をかけましたが、A児はそこから動きません。「友達とけんかして、すねてるのかな。」「寒いから嫌なのかな。」私は、A児の近くまで行ってみました。A児は植木鉢の雪をのけていました。「花に雪がかぶっているから、花が寒いかもしれん。」A児の優しさが私の心を温かくしてくれた出来事でした。
また、砂場遊びをしていたときのことです。山や川を作る子、カップを使ってお菓子やジュースを作る子、思い思いの遊びを楽しんでいました。数人の子どもたちが大きな山を作り、トンネルを掘り始めました。「あ、手が届いた。」向かい合って掘っていたB児とC児は手がつながったと大喜び。そのうち、園児全員が集まって、トンネルを掘り始めました。最後は、みんなが砂場に大の字になって記念撮影。子どもたちは、自分たちでどんどん遊びの世界を広げていきました。
隣接する小学校の1、2年生たちとの交流活動を積極的に行いました。小学生が園児を気遣いながら、また、リードしながら遊ぶ姿は微笑ましく、しっかり遊び込むことによって、新しい気付きや学び合いが可能となります。幼児教育と小学校教育をつないでいくことの大切さを実感しました。


本市では、幼児教育と小学校教育の接続を意識した取組をこれまで以上に進めていきたいと考えています。そのために、必要な架け橋期プログラムを作成したり、遊びの延長としての学びを活かす授業形態や、子どもの興味や好奇心を引き出す支援の在り方について研究したりしていく計画です。これらの取組により、子どもたちがスムーズにその時々の環境に馴染み、学びへの意欲を持ち続けられることを目指しています。幼児教育から小学校教育への接続は、未来の子どもたちが自ら生き抜く力を培っていくために必要なものであると考えます。
「遊びは学び 学びは遊び ”やってみたいが学びの芽”」幼児教育から学ぶことはたくさんあります。これからも、たくさんの学びを伝えていきたいと思います。