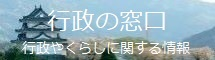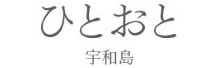本文
教育長通信「あおぞら」vol.7 公民館と共に
7月になりました。四国地方の梅雨明けが発表されたのが6月27日。統計開始以降最も早く、6月の梅雨明けは初めてだそうです。子どもたちにとっては、夏休みが待ち遠しいことでしょう。真っ赤な顔をして汗をかきながら登校する姿、教室に入ってランドセルを下ろすと背中に汗をびっしょりかいている姿、おいしそうにごくごくと水筒のお茶を飲む姿、まさに夏本番です。と同時に気を付けなければならないのが熱中症。それは、先生も同じです。授業中も休み時間も忙しく動き回って、水分補給が後回しになることがあります。子どもたちも、先生たちも、そして皆様も、こまめな水分補給を行い、熱中症予防に努めてください。
さて、公民館の話をしましょう。みなさんにとって、公民館は、どんな存在ですか。どんな思い出がありますか。
私の子ども時代の思い出は、公民館内にあった図書室です。小学生の夏休みには、しょっちゅう図書室に通い、宿題をしたり、読書をしたりしていました。祖父が公民館で書道を教えていたので、夜一緒に行っていたことも覚えています。そういえば、祖母もヨガを習いに行っていました。今も昔も、公民館はみんなの学びと憩いの場です。
教員になってからは、学校と地域を結ぶ核となる存在として、いろいろな活動や行事を一緒に行いました。花いっぱい運動やもちつき、七草がゆを食べる会や三世代交流会、防災訓練やペタンク大会、なわとび大会などもありました。各地域で特色ある活動を共に行い、学校を助け、学校を支えてくださいました。
校長になって初めて赴任した学校では、地域の様子が全く分からなかったので、当時の公民館長さんにお願いして、地域を案内していただきました。時間をかけて、いろいろなところを案内してもらい、地域の方を紹介していただくことで、距離が一気に縮まった気がしました。公民館長さんに校区を案内していただくことは、次の学校に異動してもお願いしました。自分だけでは気付かない地域の特色を直接目で見て知ることが、その後の学校経営に大いに役立ちました。こうした経験を通して、公民館は学校の力強い伴走者であると実感しています。
本市では、全ての小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールの仕組みを導入しています。さらに、全ての小中学校に地域学校協働本部を設置し、地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)を配置しています。すなわち、「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」の実現を目指しているのです。
その取組の一つとして、本市では、公民館長・主事と地域学校協働活動推進員、学校関係者が集い、合同研修会を行っています。公民館・推進員・学校それぞれの立場から、子どもと地域をつなぐ取組や自分たちにできることを協議しています。互いの立場を理解し、共感し、次へ進む意義ある研修会となっています。


【合同研修会の様子】
私は、学校と地域をつなぐ大切な役割を担うのが、公民館に集う人々であると考えます。公民館は、地域社会の拠点として、学校に対して教育支援や地域交流の場を提供する役割を果たしています。また、地域の方々との交流を通して、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育む機会を提供したり、地域の歴史や文化に触れる体験を通じて、ふるさとへの理解を深める支援を行ったり、学校教育を補完・充実させる重要な存在となっています。
公民館の役割は、実に多岐にわたります。私は、未来を生きる子どもたちの健やかな成長を支える重要な存在として、大変期待をしています。子どもたちが、そして大人たちが、安心して集える持続可能なコミュニティの場として、様々な可能性を広げていってほしいと願っています。


【宇和津幼稚園と宇和津公民館が一緒に行った米作り】