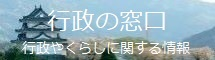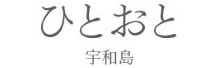本文
酒づくり特区について
酒づくり特区とは
「酒づくり特区」とは、「構造改革特別区域法」に基づく「酒税法の特例措置」が適用された特定地域のことです。この制度は、地域の農産物に付加価値を与え、地域経済を活性化させる目的で、酒類製造に関する規制を緩和するものです。主な規制緩和内容としては、酒税法で定められている酒類の最低製造量基準を満たさなくても、一定条件の下で酒類製造免許を取得できる点が挙げられます。
“牛鬼の里 うわじま” 虹色酒づくり特区
平成20年7月9日付けで、宇和島市全域が構造改革特別区域法に基づき、「“牛鬼の里 うわじま” 虹色酒づくり特区」として認定されました。
規制緩和内容について
対象事業(1) 特定農業者による特定酒類の製造事業(農業者が自ら生産した米や果実を原材料として、濁酒・果実酒を製造する場合)
構造改革特別区において、農家レストラン(飲食店)、農家民宿、旅館などを営む農業者が(自ら生産した米を原材料として)濁酒又は(自ら生産した果実を原材料として)果実酒を製造しようとする場合には、製造免許に係る最低製造数量基準が適用されず、酒類製造免許を受けることが可能となります。
対象事業(2) 特定酒類の製造事業(地域の特産物を原料とした果実酒・リキュールを製造する場合)
構造改革特別区において生産された地域の特産物(ヤマモモ、タロッコ)を原料とした果実酒又は地域の特産物(宮川早生、南柑20号、今津ポンカン、白柳、せとか、タロッコ、キウイフルーツ、あんず、梅、イチゴ)を原料としたリキュールを製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造基準(6キロリットル)が果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ、小規模事業者においても酒類製造免許を受けることが可能となります。
構造改革特別区域計画について
構造改革特別区域計画(宇和島市) [PDFファイル/206KB]
酒造免許の取得をお考えの方へ
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
酒類製造免許申請書の提出先は、製造免許を受けようとする製造場の所在地の所轄税務署です。個別の具体的な相談については、税務署の酒類指導官にお問い合わせください。
(宇和島市の場合は松山税務署(外部リンク)が所轄となります。)